電験3種・理論分野の試験対策・問題集についてをまとめました。
抵抗率と導電率の違いとは?試験対策と計算問題【電験3種・理論】
抵抗率と導電率の違い
抵抗率と導電率の違いは以下のとおりです。
- 抵抗率
- 電流の「通しにくさ」を表したもの。
- 導電率
- 電流の「通しやすさ」を表したもの。抵抗率の逆数。
電線の材質による抵抗率
| 材質 | 抵抗率[Ω⋅m] |
|---|---|
| 銀 | |
| 銅 | |
| 金 | |
| アルミニウム | |
| 鉄 |
抵抗率は銀が最も小さい(伝導率)が高いです。
しかしながら銀は高価なため、実際には銅線やアルミニウム線が用いられることが多いです。
電線の抵抗を計算する式
抵抗率![]() [Ω⋅m]、電線の長さ
[Ω⋅m]、電線の長さ![]() 、電線の断面積
、電線の断面積![]() 、電線断面の直径
、電線断面の直径![]() のとき、電線の抵抗r[Ω]は以下の式で計算できます。
のとき、電線の抵抗r[Ω]は以下の式で計算できます。
![]()
計算式から以下のことがわかります。
- 電線が長くなる→抵抗も大きくなる
- 電線が太くなる→抵抗は小さくなる
なお、抵抗率ρは電線の素材によって決まります。
導電率σは抵抗率の逆数(1/ρ)となります。
【例題1】銅線の抵抗
【問題】
直径 2mm の円形の銅線が1kmあるとします。
銅の抵抗率ρが![]() [Ω⋅m]のとき、この銅線の抵抗を求めよ。
[Ω⋅m]のとき、この銅線の抵抗を求めよ。
【解答】
![]()
【例題2】電線の抵抗
問1)抵抗1Ωの電線の長さ![]() が2倍になった場合、抵抗は何倍になるか。
が2倍になった場合、抵抗は何倍になるか。
解1)2倍
問2)抵抗1Ωの電線の断面積sが2倍になった場合、抵抗は何倍になるか。
解2)1/2倍
問3)抵抗1Ωの電線の断面半径dが2倍になった場合、抵抗は何倍になるか。
解3)1/4倍
【例題3】断面積と直径と抵抗値の関係
【問題】
直径2.6 mm、長さ10 mの銅導線と抵抗値が最も近い同材質の銅導線はどれか。
①断面積 5.5 mm2、長さ 10m
②断面積 8mm2、長さ 10m
③直径 1.6 mm、長さ 20m
④直径 3.2 mm、長さ 5m
【解答】
(断面積)=(半径)×(半径)×(円周率)より、③④を断面積に直します。
※半径=直径÷2
③の断面積は0.8×0.8×3.14≒2.0mm^2
②の断面積は6×1.6×3.14≒8.0mm^
①の導線 断面積5.5mm^2 長さ10m
②の導線 断面積8.0mm^2 長さ10m
③の導線 断面積2.0mm^2 長さ20m
④の導線 断面積8.0mm^2 長さ5m
抵抗値は断面積に反比例し、長さに比例するので最も近いのは①
関連リンク


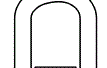
コメント